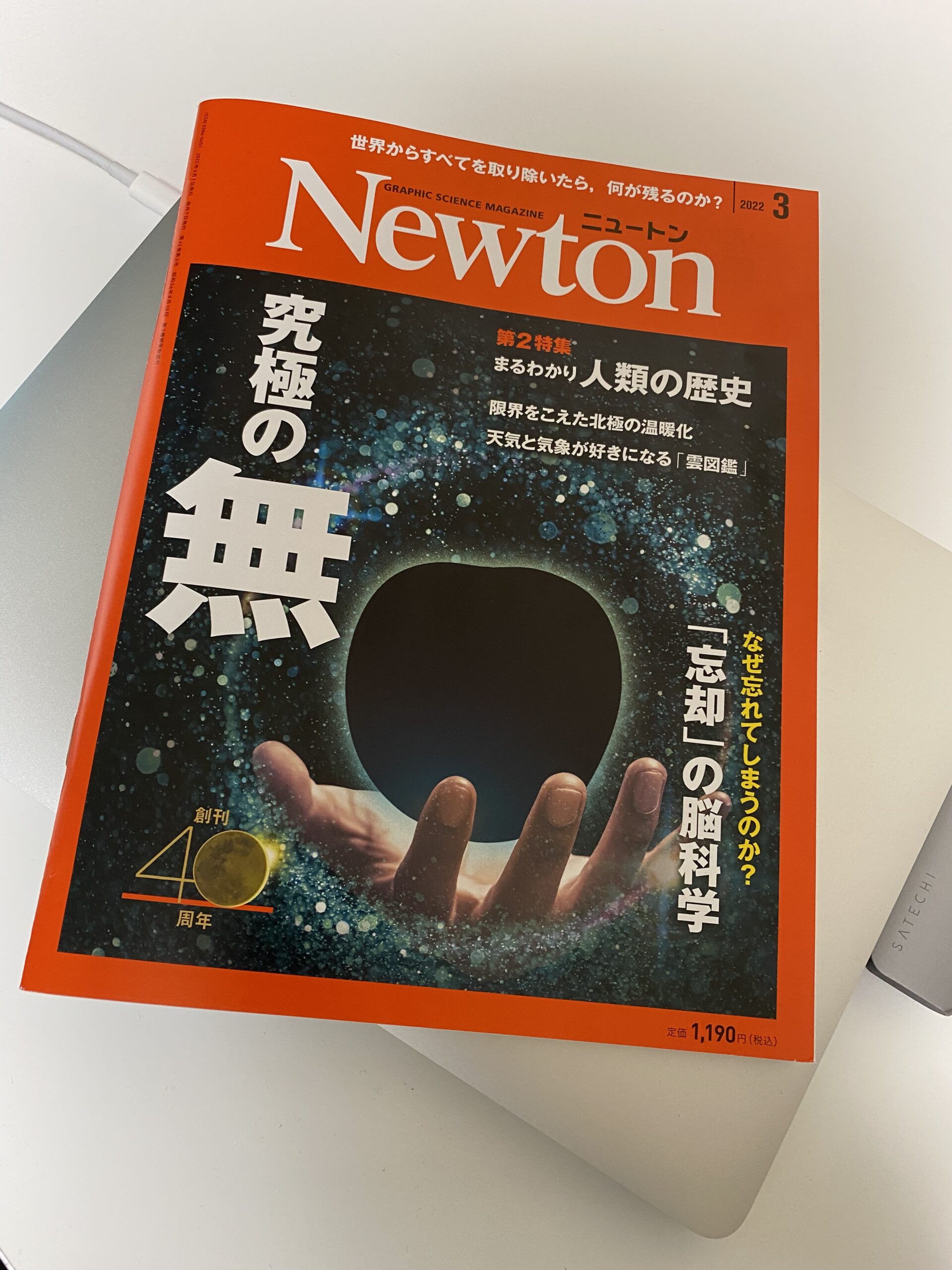BOOK STORE 〜変わる時代の中で、変わらない習慣〜
レコードショップや本屋が次々と姿を消し、ワンクリックで何でも手に入るようになった今でも、私は2週間に一度は書店へ足を運ぶ。この習慣だけは、いまだに変わることがない。
子どもの頃、町にはたくさんの小さな本屋があった。小さな店から中規模のインディペンデントな書店まで、それぞれに個性があり、そこは単なる“販売の場”ではなく、新しい情報、社会問題、時代の悩みを“見つける場”でもあった。
昔の書店には、椅子が置いてあることもあって、立ち読みどころか、何時間も本と向き合える空間だった。今で言えば、六本木TSUTAYAのような“滞在型”の書店。長居しても心地よく、知識と感性が刺激される場だった。
確かに、インターネットなら過去から現在までの作品が簡単に手に入る。しかし、私のように「いま」を知り、「これから」を探りたい人間にとっては、雑多な情報の海から“何か”を見つけ出すのは簡単ではない。
書店の魅力は、まさにそこにある。タイトルが並ぶ背表紙から、予想もしなかった出会いが生まれ、興味が掘り起こされる。気になった本を手に取って、さらに深く知りたくなったら古本屋へ。そんな探索が、私にとっての情報収集の原点だ。
7歳の頃、尊敬していた歯医者の先生の待合室に置いてあった雑誌『Newton』。内容は難しかったが、鮮明で視覚的に訴えるイラストに惹かれて、家に帰るたびにその雑誌を買っていた。科学や宇宙の知識は、理解できないままでも面白かった。20代になってようやく文章の意味が分かるようになり、それが私の“話題のネタ”の宝庫となっていた。
そんな『Newton』が2017年に民事再生を申請したとき、大きな衝撃を受けた。ちょうどその頃、街の大型書店やGMS内の本屋も次々に姿を消していた。私は本気で、「大切なネタ元がなくなったら、どうしたらいいんだろう」と不安になった。
今、インディペンデントな本屋やCDショップが、未来を見つめるような品揃えを保ち、新たな情報を発信し続けるのは本当に難しい時代だ。だからこそ、私は消費者として、少しでも応援したいと考えている。
「無くなっては困る店」で買う。期待している作品をリリースしてくれる人や会社から直接買う。それが私の基本姿勢だ。中古品ばかり買ったり、作り手にお金が還元されない形の消費はなるべく避けてきた。なぜなら、作品を世に出すには開発費だけでなく、たくさんの時間や経験の積み重ねが必要だからだ。
それは、研究を続けている組織や個人にも当てはまる。資金が回らなければ、良いアウトプットは続かない。
環境保護やSDGsといった言葉が注目される今、私は本当に大切なのは「何に共感し、どこにお金や時間を使うか」を選ぶ姿勢だと思っている。現在進行形の活動、未来へ向かう思考を応援すること。それが私なりの“消費”のあり方であり、“文化”との付き合い方だ。